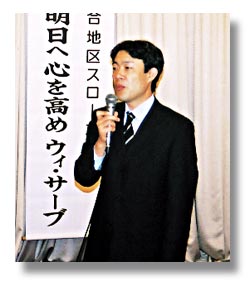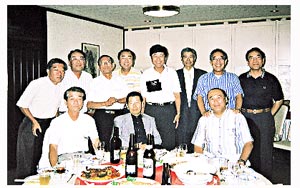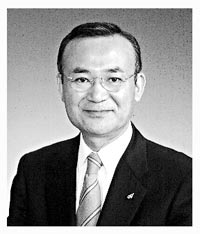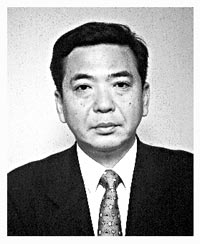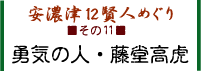丂丂丂
偡偭偒傝偟偰偰丄仢乮偵偠傘偆傑傞乯
乣334-俛抧嬫擭師戝夛丗婒晫乣

丂俀侽侽俁擭俆寧18擔乮擔乯丄怐揷怣挿備偐傝偺抧丄乽婒晫乿僌儔儞僪儂僥儖偵偍偄偰崱擭堦擭傪掲傔偔偔傞戞49夞擭師戝夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅
丂乽柌偲婓朷傊偺旘隳乿偲柫懪偪丄戙媍堳憤夛丄暘壢夛偲懕偒丄慡堳偑廤偆擭師戝夛幃揟偺巒傑傝偱偡丅
丂僆乕僾僯儞僌偱偼丄悂憈妝丄儅乕僠儞僌戝夛偱慡崙戝夛偺弌応傪壥偨偟偨導棫婒晫彜嬈偺悂憈妝晹偵傛傞墘憈偲僼儔僢僌僷僼僅乕儅儞僗偱擌乆偟偔枊偑奐偒丄戝偒側攺庤偺拞丄搉曈僈僶僫乕偲晇恖偑擖応偝傟傑偟偨丅堦擭娫偺偛嬯楯傕偙偺堦弖偱挔徚偟偵側傞傫偩傠偆側偲丄偄偮傕幃揟傪尒偰偄偰巚偄傑偡丅乮枹宱尡側偺偱杮摉偺偲偙傠偼傢偐傝傑偣傫偑乧乯
丂偦偺屻傕偄偮傕捠傝恑峴偟偰偄偒丄僈僶僫乕僄儗僋僩偺徯夘丅偦偟偰垾嶢丅
丂師婜僉儍價僱僢僩傛傝棃擭偼俆寧16擔乮擔乯丄堳曎偺抧偱戝夛奐嵜偺俹俼偑偁傝僼傿僫乕儗丅
丂偦偺屻偺僈僶僫乕僘崸恊夛傕婒晫偺偒傟偄偳偙傠偺梮傝偲儗乕僓乕僔儑乕乭岝偲壒偺嵳揟乭偺擇偮偱丄憗偔價乕儖傪堸傒偨偄巹側傫偐偼丄偡偭偒傝偟偰偰椙偐偭偨偲巚偄傑偟偨丅憤偠偰丄偡偭偒傝偟偰偄偰僗儅乕僩側戝夛偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅
丂丂
儂乕儉儁乕僕偺妶梡傪両
乣PR丒夛曬丒僀儞僞乕僱僢僩埾堳夛扴摉椺夛乣
搶嫗丒柤屆壆偐傜島巘
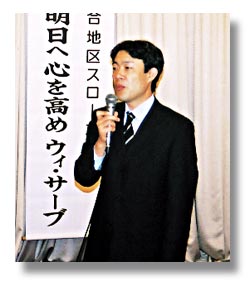
丂俆寧23擔乮嬥乯丄忋婰埾堳夛偺扴摉偱椺夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅
丂俴媣暷埾堳挿偺偍悽榖偵傛傝丄僉儎僲儞斕攧乮姅乯傛傝島巘傪偍彽偒偟丄乽巇帠偵妶偒傞僀儞僞乕僱僢僩乿偲偄偆僥乕儅偱偍榖傪偄偨偩偒傑偟偨丅
丂偙傟偐傜偺斕攧曽朄偺堦偮偲偟偰儂乕儉儁乕僕傪妶梡偝傟偰偼偳偆偱偡偐偲偄偭偨撪梕偱偟偨偑丄摉擔係柤偺曽偑棃傜傟丄偦偺偆偪俀柤偼傢偞傢偞搶嫗偐傜偍墇偟偄偨偩偄偨偲偺偙偲偱偟偨丅偍榖偟偄偨偩偔帪娫偑彮側偐偭偨偙偲丄怽偟栿側偔巚偭偰偍傝傑偡丅
夛挿攖偼俴尨揷壚岾
乣僑儖僼晹夛庢傝愗傝愴乣
怴擭搙偼俈寧19擔乮搚乯丒楅幁俠俠偐傜

傗偭傁傝丄夛挿傪彆偗偨偛朖旤偐丠
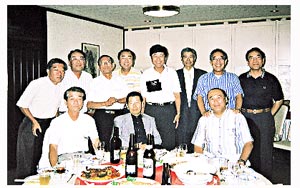
丂俇寧14擔乮搚乯丄堦埵偺栘偱嶌傜傟偨夛挿攖傪傔偞偟偰丄捗俴俠僑儖僼晹夛偺嵟廔愴偑峴傢傟傑偟偨丅慜敿偼側傫偲偐傕偭偰偄偨揤岓傕拫偐傜偼戝塉偵側傝丄僐儞僨傿僔儑儞偺埆偄拞丄俴尨揷壚岾偑39偱夞傝丄屵慜拞偺43偲偺僩乕僞儖82偲偄偆慺惏傜偟偄僗僐傾偱桪彑丅俇帪偐傜応強傪怴挰偺憦廤墤偵堏偟惙戝偵懪偪忋偘夛傪奐嵜偟傑偟偨丅
丂怴擭搙偼丄晹夛挿偵俴摗攇寬堦丄姴帠偵俴嫶杮傪昅摢偵丄俴堫敤丄俴楅栘丄俴尨揷壚岾偺儊儞僶乕偱俈寧19擔乮搚乯丒楅幁僇儞僣儕乕傪旂愗傝偵奐嵜偝傟傞丅懡悢偺偛嶲壛傪偍婅偄偟傑偡丅
仭怴擖夛堳徯夘仭
丂俀柤偺怴擖夛堳傪寎偊傑偡丅偄偢傟傕岎戙夛堳偱丄偔偟偔傕宑墳戝妛偺摨憢偺偍擇恖偱偡丅
丂丂
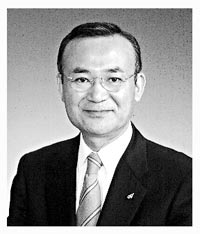
俴栰楥徍旻
|
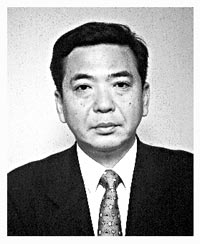
|
俴栰楥徍旻乮偺傠丒偁偒傂偙乯乛嶰廳導丒抦帠乛徍榓21擭8寧28擔惗傑傟乛帺戭丒捗巗娤壒帥挰446-20乛岾悽晇恖乛宑墳戝妛岺妛晹懖偍傛傃摨戝妛堾廋椆乛廜媍堾媍堳係婜丒徏嶃巗挿傪宱偰暯惉15擭嶰廳導抦帠
俴崅栰尦椙乮偨偐偺丒傕偲傛偟乯乛挬擔惗柦曐尟憡屳夛幮丒嶰廳巟幮挿乛徍榓30擭1寧1擔惗傑傟乛帺戭丒捗巗娵擵撪梴惓挰15-6僔儍僩乕僇儚僀乛恀媩晇恖丒挿抝峗暯乛宑墳戝妛朄妛晹懖嬈
丂丂
丂丂丂
丂丂丂
|