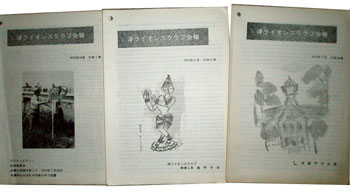五月晴れの下、ライオン集合
─334-B地区年次大会─
2008年5月18日(日)

手堅く、スムースな運営が好感

334─B地区年次大会が、5月18日(日)、四日市文化会館をメイン会場に開催され、我がクラブからは、事務局を含め33名が参加しました。昨年の揖斐川からまたもう1年が経ってしまった、というのがまず一番の感想です。今年の大会は、例年に比べ、質実で、手堅くかつスムーズな運営であったというのが、2番目の感想です。最近の大会でよく見られたフォーラムも無く、時間通り、進行していきました。オープニングの諏訪太鼓とハマダキューティーの子供達のダンスで雰囲気を和らげ、L豊田良郎大会会長(例によって白のタキシード)の開会ゴングで始まり、来賓挨拶、年次大会決議事項の報告、アクティビティーの目録贈呈等々、整斉と議事が進行しました。
皆さんにご報告しておくことは……。
1. 今年国際大会が開かれるタイのバンコクからホスト委員会委員長が出席されており、たくさんのLが登録するようにとのアピールがありました。
2. 来年のスローガンは「築こう 奉仕の山脈 熱き心で…」です。
3. 大会記念事業の一つは、ライオン像(Cab.─kun)の設置一式450万円。
四日市の市役所近くの商工会議所前に設置され、ローマの休日のライオンの口をモチーフに考えられたそうです。浄財をその口に投入するとウオーという雄たけびが流れる仕組みとか、皆さん四日市に行かれた際は一度お試しを。
4. ガバナー大賞は津西クラブ他3クラブ。会員増強とCSF˘貢献がキーワード。我がクラブは、社会福祉優秀賞を頂きました。
5. 天気晴朗。やっぱり天気が良いと気持ちもハッピー。広場の「からくり山車の大入道」も笑っていました。
さて、来年は多治見、そして再来年はいよいよ津。L石井ガバナー予定者頑張って!
というか、皆で支えていきましょう。そのとき我がクラブも50周年。どうなりますことか…。なるようになる。楽しみましょう。(L稲畑会報委員長・記)
6名の新入会員を迎えて
=4月第2例会:4月25日=
チャーターナイト記念例会

交代会員のL木村(左)とL真柄(右)

4名のJC卒の気鋭の新人
本年度のチャーターナイト記念例会は、6名の新入会員を迎えて開催。
L木村嘉伸・(株)デンソー三重、L真柄哲朗・三井住友海上火災保険(株)の両名は交代会員。L松川智郎・(株)松川興行所、L久保井仁・(有)久保井工業、L藤川博・(株)藤川工務店、L牛場章雄・(株)菊谷電気商会はそれぞれ津青年会議所を卒業した気鋭の新人。
さっそくチャーターナイトのイベントとして6名の新ライオンにスピーチをしていただいた。
しかしまあ、語り口のスムースなこと。そして、自慢や宣伝、信条をとくとくと述べることなく、爽やかな語り口に驚かされた。まさに、クラブにどっぷりと浸かった先輩ライオンに「初心忘るべからず」と言外に諭された感があった。
|



 00000
00000
 00000
00000





 00000
00000